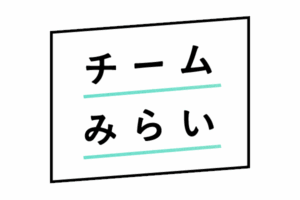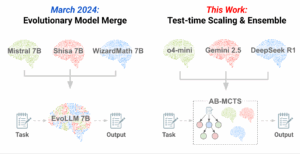システム開発者が読み解く:チームみらいのマニフェストが描く日本の未来
はじめまして、Tak@です!普段はシステムインテグレーターとして様々なシステム開発に携わりつつ、Webサービス開発を楽しんでいます。
このコラムでは、先日発表された「チームみらいのマニフェストver.1.0」が、私たちの暮らしやビジネスにどのような影響を与えるのか、システムを作る側の視点から考えてみたいと思います。
チームみらいが目指すもの:誰も取り残さない社会づくり
チームみらいは、AIをはじめとするデジタル技術の力を活用して、社会から誰一人として取り残さない未来を築くことを目指しています。彼らの考えは、日本が直面する現在の厳しい状況から生まれています。
過去20年、私たちの国では平均年収が伸び悩み、国内総生産(GDP)も停滞してきました。その一方で、少子高齢化は進み、労働力の中心となる生産年齢人口は減り続けています。
世界中でインターネット関連の新しい産業がどんどん生まれている中、残念ながら日本はデジタル分野で遅れをとっている、という認識があります。
このような状況を乗り越えるため、チームみらいはAIの能力が驚くほどの速度で向上している今こそ、技術を良い方向に使い、これらの課題を解決する大きな機会だと捉えています。
彼らは、政策を実現するための三つの段階を提案しています。
それは、「デジタル時代の当たり前をやりきる」、「変化に対応できる、しなやかな仕組みづくり」、そして「長期の成長に大胆に投資する」というものです。例えば、複雑な行政手続きをデジタルで扱いやすくしたり、AIを使って教育の質を向上させたりするアイデアが含まれています。
私がシステム開発に携わる者として、彼らのこの方向性に深く共感しています。
技術は、ただの道具ではありません。
それは、私たちの社会が抱える問題を解決し、人々の生活をより豊かにするための大きな可能性を秘めていると私は感じています。このマニフェストは、その可能性を具体的に示し、私たちに未来への期待を与えてくれます。
最初の大きな一歩:「デジタル時代の当たり前」をやりきる
マニフェストの最初の段階は、「デジタル時代の当たり前をやりきる」という明確な目標を掲げています。これは、日本が抱える課題の多くは、実は技術的に目新しいものではなく、すでに確立されているデジタル技術や方法を導入し、それを社会に根付かせることで解決できる、という考えに基づいています。
裏を返せば、現状の日本の社会には、デジタル化を進めることで得られる「伸びしろ」がたくさんあるということです。
行政サービスをより身近に
行政手続きを「行かせない、書かせない、待たせない、迷わせない」ものにする、という目標は、多くの人にとって非常に魅力的なものでしょう。オンラインでの手続きをさらに進め、マイナンバーカードの活用を広げることで、役所に出向く必要がなくなる手続きが増えることが期待されています。
例えば、市民がオンラインで意見を出し合うことができる「いどばたシステム」の開発は、議論や合意形成を助けるための重要な取り組みです。
また、パブリックコメント(政策などに対する意見募集)に寄せられる大量の意見をAIで効率的に分類・分析する「広聴AI」の開発も進められています。
これにより、行政はより多くの意見を、少ない労力で素早く把握できるようになります。イギリスやアメリカでの類似プロジェクトでは、意見の重複をなくしたり、テーマを自動で抽出したりすることで、作業時間が大幅に減ったという成果が出ています。
さらに、政治資金の流れを誰でも簡単に見ることができる可視化ツールの開発も計画されています。これは、政治の透明性を高め、私たち国民が政治に興味を持つきっかけにもなるはずです。
地方自治体が独自のアプリを開発するのを助けるために、オープンソース(誰もが自由に利用・改変できる形式)でシステムを提供し、全国に広げていく支援も行われます。
行政が外部の企業にシステム開発を発注する際も、事前にプロトタイプ(試作品)を作ることで、どんなシステムが必要なのかを明確にし、無駄なコストを減らそうとしています。
公務員の働き方を改善するためにも、AIやITが使われます。FAXや紙の書類をなくし、最新の業務ツールを導入することで、職員のデジタル技術を使う力を高めるのです。
AIアシスト型のワークフローは、パブリックコメントの分類や分析を助け、紙の資料を読み取って検索可能にしたり、庁内の文書を横断的に検索できるようにデータベース化したりします。また、法律を作る際の支援業務でもAIが活用され、類似の法案を探したり、過去の議論を分析したりするツールが開発されます。
法令の情報をより使いやすくする取り組みも進みます。
現在、複雑で分かりにくい法令の条文も、改正履歴や施行日が可視化され、企業や自治体が自社のルールを自動で更新できるようにAPI(システム同士をつなぐ仕組み)で情報提供される予定です。
選挙の立候補手続きも、紙と対面が中心だったものを全面的にオンライン化し、地域ごとの違いをなくして全国で同じように手続きできるようにする計画もあります。
子育てと医療の負担を減らす
子育ての分野では、「デジタル母子パスポート」の実現が掲げられています。妊娠中の体調が不安定な時期に、母子手帳を取りに行ったり、予防接種のスケジュールを紙で管理したりする負担が、このパスポートで大幅に減ると期待されています。
また、AIと専門家が協力して、子育てに関する相談ができるポータルサイトの設置も検討されており、必要な情報を必要な人に届ける「プッシュ型支援」が実現されるでしょう。
医療の分野では、オンライン診療の普及を加速させ、薬の受け取りも自宅でできるような仕組みを整えることで、「通院のない通院」を目指しています。
画像診断AIの導入も進められ、医師の負担を減らしつつ、診断の精度を高めることが期待されています。
病院での待ち時間を減らすために、スマート受付やキャッシュレス決済の導入も支援されます。
私は、このような取り組みが、日々の忙しさの中で医療を受けることが難しいと感じている方々にとって、大きな助けになると考えています。
福祉と教育の質を高める
福祉の分野では、テクノロジーを使って、支援が必要な人が適切な福祉サービスに迷わずアクセスできるようになります。例えば、AIチャットボットが質問に答え、必要な情報を自動で知らせてくれるようになります。
また、障害年金や生活保護の認定プロセスにAIを導入することで、審査の透明性や公平性を高め、職員の作業を効率化します。情報が読み取りにくい方のために、やさしい日本語やルビ(ふりがな)付きの文章、図解、ピクトグラムなどを活用し、誰もが情報に触れやすい環境を作ることも目指されています。
教育の分野では、子どもたち一人ひとりに「専属のAIアシスタント」を届けるという、とても興味深いアイデアがあります。AIがそれぞれの学習状況や興味に合わせて学びを支え、自ら考える力を育む手助けをします。
また、教員の業務負担を減らすために、AIやITツールを積極的に導入し、先生方が子どもたちと向き合う時間を増やせるようにします。
例えば、外国人児童の家庭との多言語でのやり取りなど、AIを使えば手軽にできるようになるでしょう。子供たちのAIに関する知識や使い方を育むために、中学校に「情報」という教科を新設することや、AIに特化した先進的な高校を作ることも検討されています。
システムインテグレーターとして、私はこの「デジタル時代の当たり前」を徹底的に追求する姿勢に非常に好感を持っています。
特別な技術を新たに開発するのではなく、すでに存在する技術を社会の隅々まで行き渡らせることで、私たちの日常の多くの不便さが解消されるはずです。この取り組みは、私たちが日々の生活の中で感じる小さなストレスを減らし、より時間を有意義に使えるようにしてくれることでしょう。
変化を受け入れる力:「しなやかな仕組みづくり」
マニフェストの第二の段階は、「変化に対応できる、しなやかな仕組みづくり」です。現代社会は、国際情勢の不安定さやAIの急速な進化など、かつてない規模と速度で変化しています。
このような予測が難しい時代において、チームみらいは、大きな変化に直面しても「立ち直る力」と「素早く賢く対応する力」を持った社会システムが必要だと考えています。
行政のアジャイルな運営
行政の分野では、技術の進歩に法律の改正が追いつかないという課題があります。これを解決するために、「失敗を許容し、データに基づき素早く学ぶ政策サイクル」を導入することが提案されています。
これは、まず小規模な試作品(MVP)を作り、実際に運用しながら利用者の意見を取り入れて少しずつ改善していく、という開発手法(アジャイル開発)の考え方を政策形成に応用するものです。
これにより、高額なシステムを一括で発注して特定の業者に固定化されるリスクを減らし、状況の変化に柔軟に対応できるようになります。
税や社会保障の制度も、物価や賃金に合わせて自動的に見直される「なめらかな税・社会保障」を目指しています。所得の境目で急に不利になるような「崖」をなくし、より公平で予測しやすい制度にすることで、国民が安心して暮らせるようになります。
デジタル民主主義の深化も重要な点です。
従来のパブリックコメント制度では、意見が多すぎて行政が処理しきれなかったり、同じ意見が多数投稿されてしまう「多数派工作」の問題がありました。
チームみらいは、AIを使ってこれらの意見を構造化・可視化する「ブロードリスニング」を進め、「声になっていない声」も引き出すことを目指しています。
私は、金融系のシステム開発で公開鍵基盤(PKI)に触れ、セキュリティの重みを改めて感じました。このような市民の声を集約するシステムにおいても、透明性とセキュリティを確保しながら、建設的な議論を促すことが何よりも重要だと考えています。
これにより、価値観や利害が対立しやすい複雑な政策課題についても、AIが議論を促進し、対立を乗り越える合意形成を助けていくことができます。
医療・教育・福祉における柔軟性
医療分野では、国民健康保険法や高齢者医療確保法に定められている年齢別の自己負担割合を見直し、医療の「有効性」や「重要度」に応じて細かく自己負担を調整する制度が検討されています。
また、治療の成果に応じて医療機関に報酬が加算される「医療アウトカム評価制度」を導入し、電子カルテの標準化と連携を進めることで、医療現場の負担を減らしつつ、質の高い医療の提供を促します。
教育分野では、AIを活用して子ども一人ひとりの個性や学習の進度に合わせて、カリキュラムを「オーダーメイド」で作ることを目指しています。
現在の画一的な教育ではなく、それぞれの子供に合った学びを提供することで、より深い理解と好奇心を育むことが期待されます。また、教育データの活用を進め、AIによる効果測定と評価サイクルを導入することで、政策の効果を客観的に検証し、継続的に改善していくことも目指しています。
福祉分野では、障害のある子供とその家族への支援をより細やかに、そして迅速に行うための仕組みが提案されています。
オンラインプラットフォーム「ファミリーサポートハブ(仮称)」を通じて、必要な支援サービスや手当、施設に関する情報が一元的に管理され、申請手続きもオンラインで完結できるようになります。
AIが利用者の状況やニーズを分析し、関連性の高い制度やサービスを自動で提案する「プッシュ型支援」も実現されます。
ヤングケアラーや子どもの貧困、児童虐待といった困難な状況にある子どもたちを早期に発見し、必要な支援を継続的に届けられるよう、AIを活用したスクリーニングシステムや相談窓口の設置も検討されています。
また、障害者の雇用を増やすために、AIを使った業務ナビゲーションツールや企業担当者向けのAIコーチ機能などを開発し、経験の少ない企業でも安心して障害者を雇い続けられるように支援します。
システムインテグレーターの立場から見ると、これらの取り組みは、変化の激しい現代において、社会のシステムが柔軟に対応できるようになるための「体質改善」のようなものだと私は感じています。
一度作ったら終わりではなく、常に状況に合わせて変わり続けられる仕組みを作ることは、技術的な挑戦でもありますが、それ以上に、社会をよりよくしていくための強い意志が求められます。
未来への投資:「長期の成長に大胆に投資する」
マニフェストの第三の柱は、「長期の成長に大胆に投資する」という考えです。チームみらいは、日本の経済的な豊かさ、つまり「パイ」が縮小している現状では、いくら公平に分配しようとしても効果は限られてしまうと指摘しています。
持続的な経済成長を達成するためには、AIをはじめとする先端技術への積極的な投資が不可欠だと彼らは強く主張しています。
科学技術を国の力に
科学技術の分野では、日本の研究力が国際的に見て低迷しているという現状があります。特に、質の高い論文の数が少ないのは、研究者が本来の研究に集中できていないことが一因だと考えられています。
この課題を解決するため、研究資金の申請や報告にかかる事務的な負担をAIやITで減らし、研究者が自由に、そして長期的に研究に取り組める環境を整えようとしています。
例えば、「Research Management System(RMS)」というシステムを導入し、研究費や人材、設備を一元的に管理することで、事務作業を効率化し、不正の早期発見にもつなげます。
また、博士課程に進む学生が少ないという問題や、研究者のキャリアパスが限られている問題にも取り組んでいます。
企業や政府機関との間で人材が行き来できる「キャリアリターン制度」や「人材シェアリング制度」を構築し、研究者がアカデミア(大学・研究機関)と産業界の間を柔軟に移動できるように支援します。
これにより、研究成果が社会で使われるまでのスピードが上がり、新しい技術が生まれやすくなるでしょう。
さらに、ディープテック分野、つまり、実用化までに時間がかかり、技術的なリスクも高いけれども、社会に大きな影響を与える可能性を秘めた技術(例えば、ロボット技術、レーザー技術、マテリアル科学、再生医療、宇宙技術など)への集中的な投資も行います。
これらの分野は、将来の日本の国際競争力を左右する鍵となると彼らは見ています。寄付を通じて大学が研究資金を集めやすくするための税制改正も検討されており、アメリカの「ドナー・アドバイズド・ファンド(DAF)」を参考に、日本版DAFの設立を目指しています。
教育と産業への大胆な投入
教育分野では、AIの活用による業務効率化で教育予算を増やし、子どもたちの好奇心や「はじめる力」を育む教育に投資する方針です。
EdTech(教育テクノロジー)の開発と学校への導入も積極的に支援し、高速なインターネット環境や高性能な端末を全国の学校に整備することを目標としています。
産業分野においては、中小企業を含む全ての企業がAIを業務に取り入れられるよう、財政・税制上の支援や、AIに関するスキルを学び直す「リスキリング」の支援を行います。
これにより、日本の産業全体の生産性を高め、国際競争力を強化することを目指します。自動運転や空飛ぶクルマといった最先端技術の社会実装を加速させるために、実証実験ができる特区を設けたり、産官学が連携して事業化までを一貫して支援する体制を整えたりする計画もあります。
また、企業がAIを活用する上で懸念される情報セキュリティのリスクに対して、情報管理ガイドラインの策定やセキュリティ対策の支援を行うことで、安全なAI導入を促します。
AIの普及には膨大な電力が必要となるため、大容量の電源を確保し、ゼロエミッション社会の実現と両立させるための技術開発や設備投資を加速させることも、エネルギー戦略として盛り込まれています。
経済財政の運営においても、AIの加速的な発達などの不確実な未来に備えるため、「シナリオプランニング」を強化する考えです。これは、例えば人間レベルの知能を持つAI(AGI)が出現し、社会に大きな影響を与えた場合にどう対応するかなど、複数の未来のシナリオを想定し、事前に政策対応を検討しておくというものです。
私は、システムインテグレーターとして、長期的な視点での投資がいかに重要であるかを日々の仕事の中で感じています。すぐに成果が出なくても、未来の社会の基盤を作るための地道な投資は、やがて大きな実を結ぶはずです。
このマニフェストが示す、未来を見据えた大胆な投資計画は、日本の社会を力強く前に進めるための原動力になると信じています。
考察:システムインテグレーターの視点から
チームみらいのマニフェストを読み込み、私がシステムインテグレーターという立場から特に強く感じたのは、「技術を社会にどう具現化していくか」という具体的な視点です。
単に「AIを導入する」と宣言するだけでなく、それが現場の人々の負担をどう軽減し、どのように私たちの生活を豊かにするのか、という点にまで深く掘り下げているのは、私たちのシステム開発の仕事と非常に多くの共通点を持っていると感じます。
行政手続きのオンライン化や医療現場のデジタル変革など、これらの取り組みはどれも、既存のやり方を変えることに対する抵抗や摩擦が大きく伴います。
それを乗り越えていくためには、ただ技術があるだけでは不十分です。実際に利用する人々の声に耳を傾け、小さな成功を積み重ねながら信頼関係を築き、少しずつ変化を広げていくプロセスが不可欠です。
彼らが掲げる「完璧なものを目指すよりも、まずは動くものを作り、そこから学び、段階的に形をよりよくしていく」という考え方は、私たちがアジャイル開発という手法で日々実践していることそのものです。
政策形成にもこの考え方を取り入れようとしていることに、私は大きな期待を抱かずにはいられません。
もちろん、全ての政策が計画通りに順調に進むとは限りません。予期せぬ課題に直面したり、技術的な限界にぶつかったりすることもあるでしょう。
しかし、このマニフェストが示す「失敗を許容し、データに基づき学ぶ」という姿勢は、予測が難しい現代において、社会を前に進める上で非常に大切な心構えだと、私は強く思います。
結びに:私たちの暮らしと「チームみらい」
ここまで、チームみらいのマニフェストが私たちの暮らしや仕事にどのような影響をもたらしうるのか、システムを構築する側の視点からお話ししてきました。
彼らが目指しているのは、私たちの社会から誰一人として取り残されることなく、誰もがよりよい未来を享受できる「デジタル共生社会」を築くという大きな目標です。
AIやデジタル技術は、単なる便利な道具というだけではありません。
それは私たちの働き方を大きく変え、日々の生活をより快適にし、これまでなかなか届かなかった声を聞き、そして、これから先の社会のあり方を作るための、計り知れない可能性を秘めていると私は考えています。
あなたは、このマニフェストを読んで、どのような未来を想像しましたか?デジタル化が進むことで、あなたの日常はどのように変化していくでしょうか?
彼らが提示する一つ一つの政策は、私たち一人ひとりの暮らしに深く関わるものです。
これからも、彼らの活動に注目し、そして時には私たち自身も積極的に声を上げて、よりよい社会を共に作っていくことが大切だと、改めて感じています。