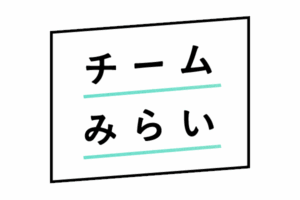「チームみらい」が示す、AIで未来を創る道のり:マニフェスト ver.0.2の要点
初めまして、Tak@と申します。普段はシステム開発に携わりつつ、趣味で生成AIを活用したツール作りを楽しんでいます。
今回は、テクノロジー、特にAIを社会変革の中心に据える政治団体「チームみらい」が公開したマニフェスト ver.0.2の核心について、皆さんと一緒に掘り下げていきたいと思います。
彼らがどのような未来を目指し、AIがその中でどんな役割を果たすのか。私のこれまでの経験と照らし合わせながら、その具体的な内容を見ていきましょう。
かつて、複雑なプログラミングに手間取りながらも、新しい技術が社会を変える可能性に心を惹かれた時代を思い出しました。
AIとテクノロジーが政策の中心に
「チームみらい」は、AIとテクノロジーで社会全体の課題を解決し、持続的な成長を実現するための要となる存在だと位置づけています。これは、単に便利な道具として使うのではなく、社会の仕組みそのものを変える力として見ている、という彼らの強い意志の表れだと感じます。
政策をみんなで作る「対話型マニフェスト」
彼らは、「マニフェスト バージョン0.1(超初期版)」という形で、まだ議論や作業の途中にある政策をあえて公開しています。これは、国民からの率直な意見や批判を積極的に受け入れ、それによって政策をより良くしていくという考えに基づいているからです。
一番良い政策は、多様な声を集めることで生まれる、と彼らは考えているのでしょう。
この「対話型マニフェスト」を実現するために導入されているのが、オープンソースで開発された「いどばたシステム」というAIです。このシステムを使えば、マニフェストの内容についてAIに直接質問したり、議論を交わしたり、さらには政策の変更や改善の提案書をAIに作ってもらうことまで可能です。
これらの提案は自動的に「チームみらい」の政策担当者に届き、検討されます。
これは、国民がオンライン上で政策づくりに深く関わる「熟議」という仕組みを目指すもので、いわば「広聴AI」の役割を果たすことになります。最終的な決定は「チームみらい」が行いますが、これは責任の所在をはっきりさせるためであり、単なる多数決とは違うとされています。
国民の声を聞く「ブロードリスニング」
さらに、「チームみらい」は、めまぐるしく変わる世界情勢やAIの進歩に対応できるよう、変化に強い柔軟な仕組み作りを重視しています。その一環として、「ブロードリスニング」という技術を活用し、一人ひとりの国民の声をより早く、より深く、継続的に集めて政策に反映させようと提案しています。
これは、まさに「デジタル民主主義」の実践であり、これからの時代に合わせた新しい政治の形と言えるでしょう。
社会や行政をデジタルで動かすAI活用
「チームみらい」の政策の第一歩は、AIやITなどのデジタル技術を当たり前に活用し、まず目に見える成果を出すことです。日本ではデジタル化が遅れている部分が多く、これを行うだけでも大きな「伸びしろ」があると彼らは見ています。
日常が変わるデジタル化の具体例
具体的にどのような分野でデジタル化を進めるのでしょうか?
- 医療分野:例えば、オンラインでの診療と薬の宅配を組み合わせることで、実際に病院に行かなくても診察を受けられる「通院のない通院」を目指しています。また、画像診断AIの導入を進めることで、診断の正確さを高めると同時に、医師が足りないという課題の解決にもつなげようとしています。
- 行政手続き:確定申告のように、これまでは複雑だった行政手続きを、エストニアの事例にならって自動計算・引き落としにするなど、オンラインで完結させることを提案しています。これは、「行かなくてもいい、書かなくてもいい、待たなくてもいい、迷わなくてもいい行政」を実現しようというものです。
- 子育て支援:母子手帳をデジタル化し、「デジタル母子パスポート」を作ることで、補助券やワクチンの管理を自動化したり、面倒な紙の手続きをなくしたり、つわりで大変な時期に外出せずに済むようにしたりと、子育て世代の負担を減らすことを目指しています。
- 教育分野:全ての生徒がAIを使えるようにすることで、効率的に学習できる環境を整え、AIを使える人と使えない人の「AI格差」をなくそうとしています。私自身も「AI学習プランナー」というツールを開発して、目標達成のための学習計画をAIが提案してくれるようにしていますが、このようなAI活用が教育現場でもっと広がるのは素晴らしいことだと感じます。
変化に対応できるしなやかな社会をAIで
AIの性能は驚くほどの速さで向上しており、それが経済、産業、教育、行政、科学など、あらゆる分野を急速に変えています。だからこそ、「チームみらい」は、社会全体がこうした変化にすぐに対応できるような柔軟さがとても重要だと強調しています。
AIが導く高度な判断と未来の仕組み
AIは、複雑な現実の状況に合わせて、より高度な判断を下せるようになります。
- 経済財政運営:例えば、AGI(人間と同じくらいの知能を持つAI)が早く開発され、産業に大きな影響を与えた場合など、さまざまな未来のシナリオを予測し、それに対して大胆な対策を事前に検討できるような仕組みを強化することを提案しています。
- 税制:今の税制は、所得や年齢といった一部の情報だけで一律に決められている部分があります。しかし、「チームみらい」は、個人の貯蓄額、景気の動き、産業ごとの状況など、より多くの情報に基づいて、AIが税金の仕組みを設計することを考えています。これにより、より実情に合った、公平な税制が実現できるかもしれません。
- 教育:年齢で区切る一律の教育ではなく、一人ひとりの個性や興味、関心に合わせて、AIチューターが細やかな指導を行うことを提案しています。これは、子供たちが自分のペースで、本当に学びたいことを深める手助けになるでしょう。
長期的な成長に向けたAIとテクノロジーへの投資
「チームみらい」は、AIが進化する時代にふさわしい成長戦略として、長期的な視点で大胆な投資を行うことを第三のステップに掲げています。これは、今の成果だけでなく、将来の日本を強くしていくための重要な取り組みです。
- 科学技術への投資:基礎研究への助成を増やしたり、世界トップレベルの研究者を日本に呼び込んだりするなど、科学技術の発展に力を入れることを考えています。
- エネルギーの安定供給:AIの利用が増えるにつれて、データセンターの電力需要も高まります。これに対応するため、地政学的なリスクが低い海外にデータセンターを作ることも提案されています。
- 文化の振興:AIがどれほど進化しても、人間が人間らしく、尊厳を持って生きていくためには、文化が不可欠であると彼らは考えています。そのため、文化を盛り上げることも、AI時代の成長戦略の大切な一部だと位置づけられています。
「チームみらい」自身のAIとテクノロジー活用
「チームみらい」は、自分たちの政策を進めるだけでなく、その活動や組織体制そのものにもAIやテクノロジーを積極的に取り入れています。
「永田町エンジニアチーム」の設立
政党交付金を活用して、およそ10名の優れたエンジニアや研究者からなる「永田町エンジニアチーム」を立ち上げることを目指しています。このチームは、政治のDX(デジタルトランスフォーメーション)を進めることを目的としています。
ここで開発された成果はすべてオープンソースとして公開され、永続的な資金で、変化に対応しながら柔軟に進める開発(アジャイル的な開発)を行い、「デジタル公共財」を生み出すことを考えています。
国会議員の中にAIエンジニアがまだいない現状を変え、政治の中心に近い場所でAIやDXの専門家が活動することで、大きな変化を生み出そうとしているのです。
「ユーティリティ政党」としての役割
さらに、「チームみらい」は、他の政党の政策作りやテクノロジー活用、DXも積極的に支援する「ユーティリティ政党」としての役割を目指しています。これによって、硬直した政治の世界全体が進化するきっかけになることを期待しているのです。
彼らのマニフェストがGitHubで公開され、誰でも閲覧したり提案したりできるのは、まさにこのオープンな姿勢の表れと言えるでしょう。
終わりに
「チームみらい」のマニフェスト ver.0.2を詳しく見ていくと、彼らがAIとテクノロジーを単なる道具ではなく、社会全体の仕組みや人々の生活を根本から良くするための土台と捉えていることがよく分かります。
国民の声をAIで集め、行政を効率化し、社会の変化に柔軟に対応できる制度を作り、そして未来に向けて大胆に投資する。
そして、彼ら自身が「永田町エンジニアチーム」を立ち上げ、オープンソースで「デジタル公共財」を生み出そうとしている点にも注目すべきでしょう。これは、自ら手を動かし、透明性を重視する彼らの姿勢が反映されていると感じます。
AIエンジニアであり、チームみらいの党首でもある安野たかひろ氏が掲げる「テクノロジーで誰も取り残さない日本」というビジョンは、私のようにテクノロジーの可能性を信じる者にとって、とても魅力的に映ります。
彼らの目指す、AIによってよりしなやかで、持続的に成長する日本が、本当に実現できるのか、これからの動きに注目していきたいと思います。皆さんのご意見もぜひお聞かせください。