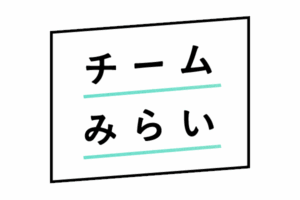政治版アジャイル開発?「チームみらい」のマニフェスト超初期版に見る未来への挑戦
生成AIを活用したWebサービス開発を楽しんでいるシステムインテグレーター Tak@です。
今回のコラムでは、先日公開された新党「チームみらい」のマニフェスト超初期版と、そのユニークな政策形成アプローチについて、私のエンジニアとしての視点から考察します。
議論の途中、作業中のものを公開する衝撃
新党「チームみらい」が、マニフェストのバージョン0.1、いわゆる「超初期版」を公開したと知りました。
通常、政党のマニフェストといえば、全ての内容が固まり、完成されたものが発表されるのが一般的ではないでしょうか。
しかし、彼らはまだ議論の途中であり、作業中の箇所も多く含まれる、未完成な状態のものを「あえて批判覚悟で」公開したそうです。これは、政治の世界では非常に珍しいアプローチだと感じました。
なぜ、未熟な段階で公開するのか?
その意図は、公開することで多くの人からの批判や意見を積極的に取り入れ、それを基に政策を改善していくためだと言います。
まだ固まっていない段階であれば、方向転換も柔軟に行えますし、早い段階で多様な人々の知恵を取り込むことができると考えているからです。
彼らは、こうした未熟なバージョンを出すことに対して、「考えがまとまっていない」といったご批判を受けるリスクがあることを認識しつつも、それを引き受ける覚悟で公開に踏み切ったようです。
これは、最も良い政策を作るやり方だと信じているからこその行動なのでしょう。
ソフトウェア開発に通じる「アジャイル」な姿勢
チームみらいの、未完成なものを早い段階で公開し、フィードバックを得ながら改善していくという姿勢を聞いて、私はすぐにソフトウェア開発の現場で用いられる「アジャイル開発」を連想しました。
アジャイルソフトウェア開発とは、予測に基づいて完璧な計画を立てるのではなく、変化への対応や個人と対話、顧客との協調、そして動くソフトウェアを重視する開発手法です。
短い期間(イテレーションやスプリントと呼ばれます)で計画、開発、デプロイを行い、実際に動くプロダクトを通してユーザーからフィードバックを得て、それを次の開発に活かすというサイクルを繰り返します。
これは、事前に全ての要件を固めてから段階的に進めるウォーターフォールモデルのような開発とは異なる考え方です。
チームみらいの今回のマニフェスト公開は、まさにこのアジャイル開発の考え方に通じるものがあると感じます。
- 未熟でも公開する:これは「動くソフトウェア」や「実働するモデル(プロトタイプ)」を早期に作り、ユーザーに提供して検証してもらう、プロトタイピング的な発想と言えます。プロトタイピングは反復型開発の一部としても位置づけられます。
- 批判や意見を歓迎する:これは顧客(国民)からのフィードバックを非常に重視する姿勢であり、アジャイル開発における適応型の価値提供の考え方そのものです。
- アップデートしていく、方向転換可能:これもアジャイルの重要な価値観である「変化への対応」を実践しようとするものです。予測困難な時代だからこそ、計画通りに進めることよりも、状況の変化に応じて柔軟に政策を修正できるしなやかさが重要になります。
- みんなで育てていく:これは「プロセスやツールよりも個人と対話」や「契約交渉よりも顧客との協調」という、アジャイル宣言の核となる価値観を政治の世界で実現しようとする試みだと捉えることができます。
行政のシステム開発は、しばしばアジャイルのような不確実性の高い開発手法が苦手だと言われますが、政治という、よりダイナミックで複雑な領域において、あえてアジャイル的なアプローチを取り入れようとする彼らの姿勢は、エンジニアとして非常に興味深く、応援したい気持ちになります。
趣味でWebサービスを開発している私自身も、小さなツールを公開した際に、ユーザーさんから「こんな機能があると便利だね」と率直な意見をいただくことがあります。
それをすぐに反映させて改修した時に、ユーザーさんが喜んでくれた経験は、私にとって大きな喜びであり、ものづくりの原動力の一つです。そうしたフィードバックループの価値を知っているからこそ、チームみらいの取り組みに強く共感します。
AIが政策作りの「相棒」に?「いどばたシステム」の可能性
チームみらいの政策形成アプローチで特に注目すべきは、国民からの意見を最大限に効果的に集約するために開発したという、AIを活用した「井戸端システム」です。
このシステムは、マニフェストの画面の横にAIとチャットする画面があり、マニフェストを読んで疑問に思ったことをすぐにAIに聞けるだけでなく、AIと議論したり、マニフェストの変更提案書を作成してもらったりすることも可能だそうです。
作成された変更提案書は、自動的にチームみらいの政策担当者に届けられる仕組みになっているといいます。
この「井戸端システム」の使い方は、まさに生成AIを社会的な課題解決やコミュニケーションに応用するお手本のように感じました。単に大量の意見を収集するだけでなく、
- 国民一人ひとりがAIと対話することで、マニフェストへの理解を深める。
- 疑問や意見をAIにぶつけることで、考えを深掘りする。
- AIに提案書の形にまとめてもらうことで、意見をより具体的に、建設的な提案として提示しやすくする。
- AIが提案書を作成・整理し、政策担当者に橋渡しする。
このようなプロセスは、単純に「意見が多いものをそのまま採用する」という多数決とは異なります。
意見は最大限聞きますし、議論のプロセスも透明にしていくと言いますが、あくまで最終的な意思決定はチームみらいの担当者が責任を持って行うとしています。
これは、責任の所在を明確にするために重要だと考えているからだそうです。人間の創造性やアイデア(国民の意見や提案)と、AIの得意とする情報収集、分析、文章生成、整理といった能力を組み合わせ、最終的な判断は人間が行うというモデルは、生成AIとの協働の理想的な形の一つではないでしょうか。
また、こうした政策が形成されていく過程そのものをシステムを通じて公開していくことは、政治に対する透明性を高めることにも繋がります。
国民にとっては、自分たちの声がどのように受け止められ、議論され、政策に反映されていく可能性があるのかが見えやすくなるため、政治への関心を高め、参加を促す効果も期待できると感じました。
未来への投資、変化に強い社会を目指して
チームみらいのマニフェストの根幹にあるのは、「テクノロジーで誰も取り残さない日本をつくる」という強い意志です。
今の日本は、再分配の議論ばかりで「パイをどうやって大きくするのか」、つまり成長への議論が不足していると彼らは指摘します。
このままでは、世界の発展から取り残されてしまうという危機感を持っています。しかし、まだ日本にはチャンスがあり、テクノロジーの力をうまく使えば状況を変えられると考えています。
マニフェストでは、日本を長期的に成長し続けられる社会にするために、3つのステップを提案しています。
まず第一に、「デジタル時代の当たり前をやり切る」こと。オンライン診療や確定申告の自動化、デジタル母子パスポートなど、ITやAIを使えばすぐにできるのに、日本では遅れていることを徹底的に実行し、短期的な成果を出そうとしています。
第二に、「変化に対応できる、しなやかな仕組みづくり」です。世界情勢やAIの進化など、予測困難な変化が激しい時代だからこそ、政策も柔軟に対応できる弾力性が必要です。AIを活用した税制アルゴリズムや教育指導など、テクノロジーによってより複雑で現実の事情に合わせた政策を実現できる可能性があると言います。ブロードリスニングで国民の意見を継続的に収集するデジタル民主主義の実践もこの一環です。
第三に、「長期の成長に大胆に投資する」こと。教育や子育てといった「人づくり」、科学技術研究、新産業創出、そして文化振興に惜しみなく投資すべきだと考えています。特に文化は、AIがどれだけ進化しても人間が尊厳を持って生きるために不可欠であり、日本の輸出産業としても重要だと位置づけています。
これらの施策は、全てテクノロジーの力を活用することで実現を目指しています。システム(テクノロジー)を通じて、変化に強く、未来への投資をしっかりと行い、長期的な成長を目指そうという方向性は、子を持つ親として非常に希望を感じますし、ぜひ実現してほしいと願っています。
結論:政治を変える新たな波に注目
新党「チームみらい」の挑戦は始まったばかりです。
組織票や後ろ盾がない中での船出は、「地盤もカンバンも鞄もない」状態だと彼ら自身が語るほど困難な道のりかもしれません。
しかし、テクノロジーの力を信じ、マニフェストをオープンに「みんなの手で育てていく」というアジャイル的なアプローチ、そしてAI「井戸端システム」のような新しい仕組みを導入しようとする姿勢は、日本の政治に新しい風を吹き込む可能性を秘めていると感じます。
この政治の新しい形について、あなたはどのように感じますか?
テクノロジーは、日本の政治や社会をどのように変えていくことができるのでしょうか。彼らの挑戦は、私たちの未来を考える上で重要な示唆を与えてくれるはずです。
今後のチームみらいの動向に、私はエンジニアとして、そして一国民として注目していきたいと思います。